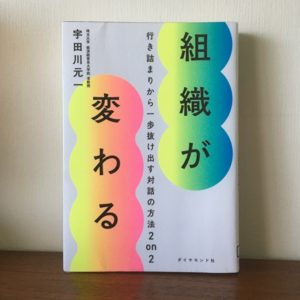問いかけの作法
安斎 勇樹/ディスカヴァー・トゥエンティワン
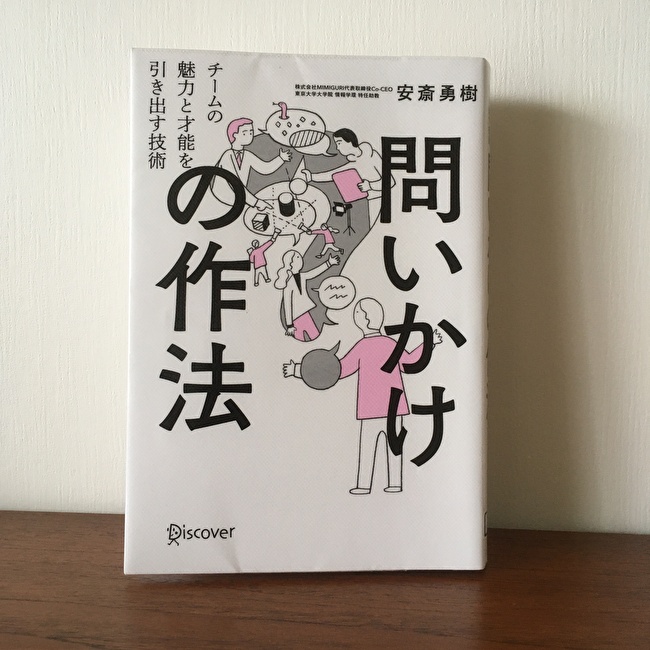
こんな悩みを持つリーダーにおすすめ
- 組織・チームにマンネリ感が漂う
- メンバーの関係性が表面的
- メンバーの目標達成への取り組みに熱量がない
ざっくり目次
はじめに
チームは問いかけから作られる
Part I 基礎編
第1章 チームの問題はなぜ起きるのか
1-1 ファクトリー型からワークショップ型へ
チームのポテンシャルとは何か
多様な個性が試行錯誤を重ねるワークショップ型の組織
1-2 ファクトリー型のチームが陥る現代病
現代病①判断の自動化による、認識の固定化
1-3 ワークショップ型でチームのポテンシャルを発揮する
チームのポテンシャルを左右する「こだわり」と「とらわれ」
事例①営業チームの個人主義を脱却させた問いかけ
第2章 問いかけのメカニズムとルール
2-1 問いかけのメカニズム
問いかけとは何か
問いかけは、相手の感情を刺激する
2-2 意見を引きだ出す問いかけの基本定石
良い問いかけとは。味方を活かす「パス」である
意見を引き出す問いかけの4つの基本定石
2-3 問いかけのサイクルモデル
問いかけの真価を発揮する、3つの作法
Part II 実践編
第3章 問いかけの作法① 見立てる
3-1 観察の簡易チェックリスト
見立てを問いかけの機軸にする
初心者のための観察ガイドライン
3-2 見立ての精度を高める三角形モデル
チームの「見たい光景」をイメージする
ときには場の目的を問い直し、変更を提案する
第4章 問いかけの作法② 組み立てる
4-1 質問の組み立て方
即興的な問いかけと計画的な問いかけ
質問を組み立てる3つの手順
4-2 質問の精度をあげる「フカボリ」と「ユサブリ」
フカボリモードをユサブリモードを使い分ける
困ったときのパワフルな質問パターンリスト
4-3 複数の質問を組み合わせる
ミーティングのプログラムを組み立てる
第5章 問いかけの作法③ 投げかける
5-1 注意を引く技術
ミーティングは「開始5分」が勝負!?
メンバーの注意を引くための4つのアプローチ
5-2 レトリックで質問を引き立てる
質問を引き立たせる「文言」の工夫
着飾りすぎない、シンプルな問いかけも忘れない
5-3 問いかけのアフターフォロー
投げかけた直後の初期反応から。必要なフォローを見極める
質問に向き合う姿勢にポジティブなフィードバックをする
おわりに
問いかけをチームに浸透させる手引き
内容
問いかけとは、相手に質問を投げかけ、反応を促進すること。その上で、良い問いかけは、「見立てる」「組み立てる」「投げかける」という3つの行為のサイクルによって成立している。
また、問いかけはチームのパフォーマンスを生み出したり、「とらわれ」と「こだわり」を明らかにして、会議や議論の場で参加者の凝り固まった考え方を解きほぐしたりもできる。
この「問いかけ」はこれからの組織運営を担うリーダーの必須スキルであり、このスキル習得に必要な理論と実践が本書で解説されている。
著書は人と組織の創造性を高めるファシリテーションの方法論について研究している安斎 勇樹氏。
Good Point
チームのポテンシャルが発揮されないのはどうしてか。
メンバー一人ひとりのモチベーションやパフォーマンスが最大限に活かされないのはなぜか。
こうしたチームの根本的な課題は「誰か」のせいではなく、チームを取り巻く時代環境の大きな「過度期」によるものだと分析。
現在の先行き不透明な時代には、試行錯誤を重ねて最適解を探求していくワークショップ型の組織運営が必要不可欠。
その際に必要なのがファシリテーションであり、「問いかけ」です。
これからのリーダーに求められるファシリテーションの土台となる「問いかけ」はぜひ身につけてほしい技術です。
心に残ったフレーズ
77ページ1行目
会社の規模が一定を超えると、複数のチームが連携しながら仕事を進めるようになり、組織のなかは「個人」「チーム」「組織」といった階層の異なる「主体」が立ち現れます。「個人のこだわり」と「チームのこだわり」があったように、「組織のこだわり」もまた存在します。それがいわゆる「理念」と呼ばれるものです。
会社を成長させようとすると、どうしても収益やビジネスモデルなど、目に見える事業課題に関心が向いてしまいます。しかしどんな組織も構成するのは「人」です。組織の創造性は、目には見えにくい「個人」の発想や、「チーム」の対話から生まれる価値の連鎖によって成り立っているのです。